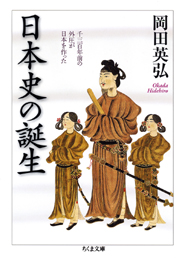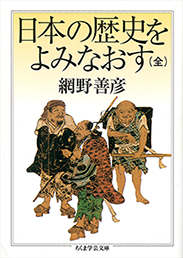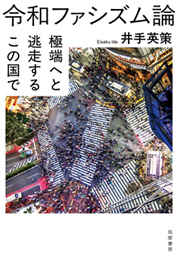朴沙羅
( ぱく・さら )朴 沙羅(ぱく・さら):1984年、京都生まれ。専攻は社会学(ナショナリズム研究)。ヘルシンキ大学文学部文化学科講師。著作に『ヘルシンキ 生活の練習』、『家(チベ)の歴史を書く』(ちくま文庫)、『外国人をつくりだす』(ナカニシヤ出版)など。
loading...
「私たち女性は、すべてを手に入れたいのです」二人の小さな子どもと移住した社会学者による、おもしろくてためになる、フィンランドからの現地レポート。
1 未知の旅へ―ヘルシンキ到着
2 VIP待遇―非常事態宣言下の生活と保育園
3 畑の真ん中―保育園での教育・その1
4 技術の問題―保育園での教育・その2
5 母親をする―子育て支援と母性
6 「いい学校」―小学校の入学手続き
7 チャイコフスキーと博物館―日本とフィンランドの戦争認識
8 ロシア人―移民・移住とフィンランド



それから一カ月して、私はまたリータに、一時間くらい相談に乗ってもらった。話題は「私が子どもに怒りすぎる」ことだ。どう考えても、親が三歳や七歳の子どもに激昂するなんてヤバい。でも怒り出したら止められないし、わりとしょっちゅう腹の立つことが起こる。どうしたらいいんでしょう。
リータの答えは、私が想像していたものとは少し違った。
まず言われたのは、「母親は人間でいられるし、人間であるべきです Mothers can be,and should be, humans! 」ということだった。
次に、怒るのはOK 。むしろ怒り方によっては子どもへの教育につながる。なぜなら、怒りや悲しみを表現することによって、子どもに「あなたがこういうことをしたり言ったりしたら、相手は怒ったり悲しんだりする」と教えることになるから 。それに今のあなたはどう考えてもruuhkavuodet peak years 人生の繁忙期なのと、怒るときは困っているときであることを考えると、何かと腹が立つのはおかしいことではない。
そもそも怒ること自体に問題はない。怒り自体には破壊的な要素はない、それが虐待的な言葉や行動に結びつかなければいい。感情それ自体はいいも悪いもない、ただあるのだから、と。そして「あなたがどんなときにも母親として我慢しなければならないと思ったり行動したりしたら、あなたの子どもたちに『母親というのは何があっても我慢しなければならない存在だ』と教育してしまうことになります」 とも言われた。いや。まあ実際そんなに我慢していない気がするのだけれども。
(中略)
親が不安定だと子どもも不安に感じるに違いないから、私はいつだって強くてどっしりして、ユキとクマにとって頼れる母ちゃんでありたい。でも、私は全然そうなっていない。私が安定するためには、私自身の人格を陶冶したり、モッチンといい関係を維持したりするだけでなく、時間とお金の余裕と、私が困ったり苦しんだり眠れなくなったりするときに助けてくれる人や仕組みが必要だ。
リータは最近、私に教えてくれた。私がコントロールすべきなのは、子どもたちではなく自分自身だと。子どもの面倒を見るということは、子どもの世界に私が入ることではなく、子どもが子どもの世界を楽しむのをただ見守ることだと。私が大人になればなるほど、私は子どもにとって安全な大人になる。そして、そういう安全な大人を子どものまわりに増やすことで、子どもたちは頼る具体的な相手を見つけられる。だから、ソサエティ(この場合は人間集団と社会福祉制度が大事なのだろう。
ユキが小さかったとき、私はあの保育園でユキを見てもらえてよかったと思う。私が眠れなくなったとき、健康診断と電話相談と育児相談を無料で受けられてよかったと思う(なお、健康診断の結果を見たかかりつけ医は「数値が良すぎる」と笑い、「で、このパーフェクトヘルシーなあなたは、私に何をしてほしいというんですか」と言った。あれは北欧ジョークだったのかも知れない)。だから私は、ユキとクマに、世の中の人はだいたい頼りになる、向こうから寄ってくる人は怪しいけど自分から助けを求めたらだいたい誰かが助けてくれる。いざとなったら世の中の仕組みに頼りなさい、と教えたい。
誰かにずっと助けてもらわなければ、私は――もしかしたら、少なからぬ人々が――あっという間に毒親になってしまう。子どもと、その子どもを主に育てる人の他に、どれだけ多くの人が関われるかによって、きっと子育ての内容は変わる。
(第5章 「母親をする――子育て支援と母性」より)
本書をお読みになったご意見・ご感想などをお寄せください。
投稿されたお客様の声は、弊社HP、また新聞・雑誌広告などに掲載させていただくことがございます。